
JSTQBのシラバスを読む【第五章】
公開日: 2025/8/4
本記事では、JSTQB Foundation Levelのシラバスを読み解き、テスト計画から欠陥管理までの重要なポイントをまとめていきます。
参考資料は「Foundation Level シラバス 日本語版 Version 2023V4.0.J01」です。
(https://jstqb.jp/dl/JSTQB-SyllabusFoundation_VersionV40.J01.pdf)
1. テスト計画

1.テスト計画書の目的と内容
テスト計画書は、テスト活動全体の指針となる重要な文書です。目的は、テストの範囲や目的、スケジュール、リソース、テスト環境などを明確にし、関係者間の共通理解を図ることにあります。
また、テスト計画書にはテスト対象やテスト方法、リスクやリスク対策なども含まれ、テストの実施を体系的にサポートします。
2.イテレーションとリリース計画に対するテスト担当者の貢献
テスト担当者は、イテレーションやリリース計画に積極的に関与し、テスト観点からのフィードバックを行います。これにより、品質リスクの早期発見や適切なテスト範囲の設定、スケジュール調整に寄与します。
アジャイル開発など反復型開発においては特に、テスト担当者の役割が重要となります。
3.開始基準と終了基準
開始基準はテストを始めるために満たすべき条件、終了基準はテストを終了するために満たすべき条件です。これらの基準を明確に定めることで、テストの開始と終了の判断が客観的かつ一貫性をもって行えます。
4.見積り技法
テスト見積もりでは、経験や過去データ、計測値などを基にテスト工数やリソースを算出します。代表的な技法には、類推見積もり、パラメトリック見積もり、専門家の意見を用いた見積もりなどがあります。
5.テストピラミッド
テストピラミッドは、テストレベルごとの割合や重要度を示したモデルです。一般的にユニットテストが基盤となり、その上に統合テストやシステムテスト、UIテストが積み上がります。
効率的なテスト設計や自動化の指針として活用されます。
6.テストの四象限
テストの四象限は、テストの目的とタイプを4つに分類したフレームワークです。「自動化向けの技術テスト」「ビジネス向けの自動化テスト」「探索的テスト」「ビジネス向けの手動テスト」などが区別されます。
各象限のバランスを取りながら、効果的なテスト戦略を立てます。
2. リスクマネジメント

1.リスク定義とリスク属性
リスクとは、将来的に発生し得る問題や障害の可能性です。属性には、発生確率、影響度、検出可能性などが含まれます。
2.プロジェクトリスクとプロダクトリスク
プロジェクトリスクはプロジェクトの進行に影響するリスク、 プロダクトリスクは製品の品質や性能に関わるリスクを指します。両者を区別し適切に管理することが重要です。
3.プロダクトリスク分析
プロダクトリスク分析は、製品に潜むリスクの特定と評価を行うプロセスです。これにより、重点的にテストすべき領域やリスク軽減策が明確になります。
4.プロダクトリスクコントロール
特定したリスクに対し、リスクの回避、軽減、受容などのコントロール策を計画・実施します。テスト活動はリスクコントロールの一環として位置付けられます。
3. テストモニタリング、テストコントロールとテスト完了
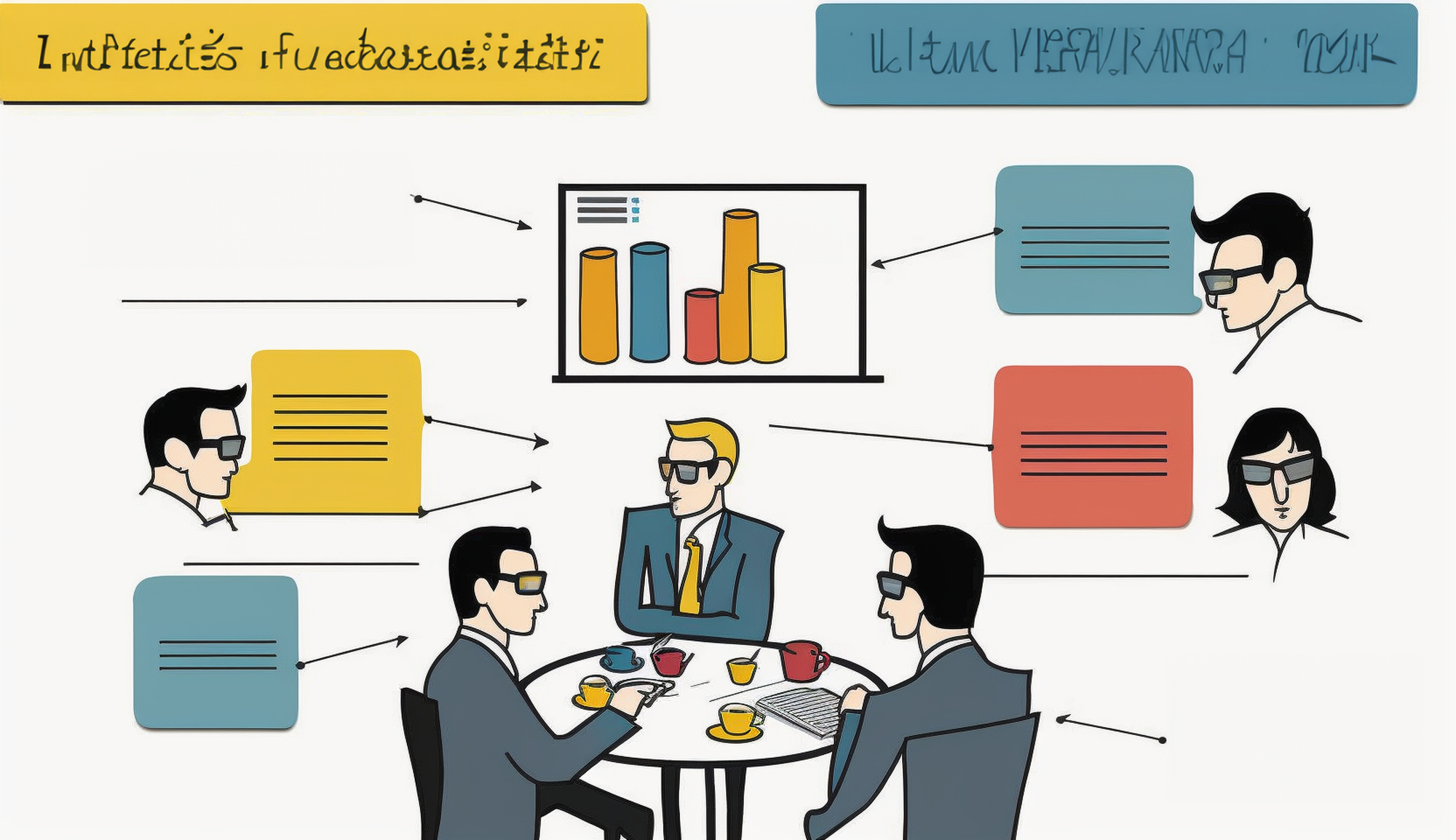
1.テストで使用するメトリクス
テストの進捗や品質を把握するためにメトリクス(指標)を使用します。例として、テストケース実行数、欠陥検出率、欠陥修正状況などがあります。
2.テストレポートの目的、内容、読み手
テストレポートはテスト結果の報告書で、目的は関係者への情報共有です。内容はテスト概要、進捗、欠陥状況、リスクなどで、読み手に応じて重点を変えます。
3.テストステータスの伝達
定期的にテストの状態を関係者へ伝達し、課題やリスクを共有します。透明性を保ち、適切な意思決定を支援します。
4. 構成管理
テスト対象物やテスト成果物のバージョン管理や変更管理を行うことです。
構成管理により、テストの再現性やトレーサビリティを確保します。
5. 欠陥マネジメント
欠陥(バグ)の発見から修正、検証、クローズまでの一連の管理プロセスです。
効果的な欠陥マネジメントは品質向上と開発効率に寄与します。
6. まとめ
以上がJSTQBシラバス第五章の要点です。
テスト計画から欠陥管理までの流れを理解することで、体系的なテスト活動の基礎を身につけることができます。
ご質問や補足説明が必要な箇所があればお気軽にお知らせください。
