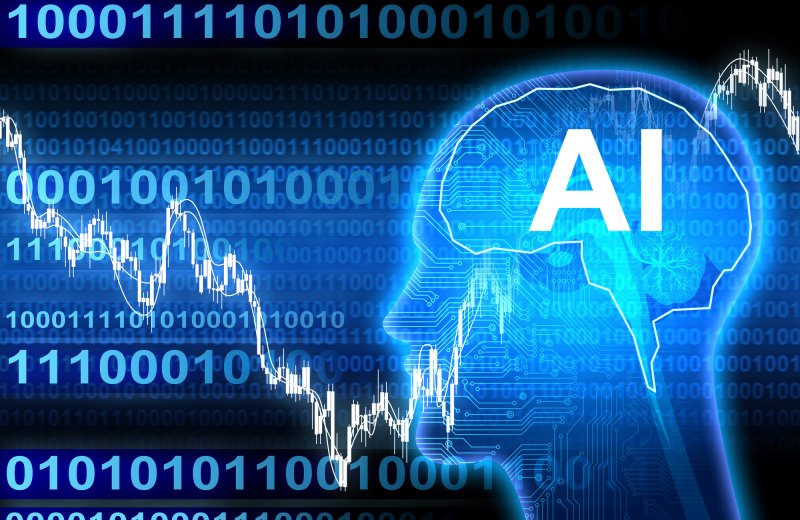
【ゼロから始めるAI】巷で噂のAIを触ってみたい 第1回
よく話題に挙がる「AI」というもの
AI(人工知能)は、ChatGPTの登場以来、「会話ができるAIが誕生した!」とSNSやメディアで大きな注目を集めてきました。今では企業が業務に取り入れ始めており、社内チャットに導入したり、テスト工程で画像認識を活用したりと、すでにAIは社会に欠かせない存在となりつつあります。私のエンジニアの友人の中には、「このままではAIに仕事を奪われるかもしれない……」と危機感を抱く人も出てきています。さらに、ゲーム開発の分野でもAIを活用した取り組みが話題になるなど、AIの可能性はどんどん広がっています。
とはいえ、世間でこれだけ話題になっていても、「AIって何となく分かるけど、実際の使い方までは分からない……」という人も多いのではないでしょうか。実は、私自身もその一人です。
だったらいっそ、自分で触って、理解を深めてみよう!
そう思い立ったのがこの企画の始まりです。AIを趣味や仕事に活かすヒントを探しながら、ゼロからAIについて学んでいきたいと思います。
このシリーズでは、「とにかく簡単に始めてみる」をテーマに、AIの基礎から実際の使い方まで、やさしく解説していきます。
1. AI(人工知能)とは?

まずは、そもそもAIとは何かをざっくり押さえておきましょう。
AIとは「Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)」の略で、日本語では「人工知能」と訳されます。
簡単に言えば、「ルールやデータをもとに、自分で考えて答えを出す仕組み」がAIです。
普通のプログラムは、決められた条件に従って動くだけですが、AIは学習を重ねて、自分で最適な答えを導き出すことができます。つまり、与えられた指示だけではなく、状況に応じて柔軟に対応できるのがAIの特徴です。
2. AIができること

AIの基本的なイメージがつかめたところで、次に「AIには何ができるのか?」を見ていきましょう。
AIの活用方法は多岐にわたりますが、まずは代表的な3つをご紹介します。
1.自然言語処理
人間の言葉を理解し、話すことができるAI技術です。ChatGPTのように、会話形式で情報をやり取りできるAIはこの分野にあたります。
赤ちゃんが言葉を覚えるように、膨大な文章から意味や文法を学習することで、自然な対話ができるようになります。
2.画像認識
画像の中身を分析し、内容を理解する技術です。たとえば「Googleレンズ」はこの代表例。カメラで撮ったものが何かをAIが判定してくれます。
大量の画像を読み込んで共通点を学習し、「これは猫」「これは靴」といった判断を可能にします。
3.音声認識
声の波形を解析して、言葉として理解する技術です。「Siri」や「Googleアシスタント」などが該当します。
音の高さやリズムなどをもとに、話している内容をテキストに変換し、意味を理解します。
このようにAIは、テキスト・画像・音声などあらゆる情報を扱い、学習によってどんどん賢くなっていきます。
かつてのプログラムは、想定外の入力に対してエラーを出して止まってしまうものでした。しかしAIは、未経験の情報であっても、「過去に学習したデータ」に基づいて適切な判断を下すことができるのです。
将来的には、AIに「こういうアプリを作って」と指示するだけで、設計・実装・テストまで自動で行う時代が来るかもしれません。
3. AIの「学習」とは?

AIが賢くなるには「学習」が必要です。では、AIはどうやって学習するのでしょうか?
実は、AIの学習には大きく分けて3つの方法があります。
1.教師あり学習
「これは猫」「これは犬」といった**正解(教師データ)**をあらかじめ与えて学習させる方法です。たとえば、猫の画像をたくさん見せて「これは猫だよ」と教え込むと、初めて見る猫の画像でも「これは猫っぽい」と判断できるようになります。
2.教師なし学習
正解を与えずに、AI自身がデータの特徴やパターンを見つけ出す方法です。データを分類したり、似たもの同士をグルーピングしたりといった使い方が得意で、「何が正解か分からない」けど「傾向を探りたい」場合に向いています。
3.強化学習
「報酬」と「ルール」に基づいて、AI自身が試行錯誤を繰り返しながら学ぶ方法です。たとえば、ゲームの中で「敵に当たるとやり直し」「ゴールにたどり着いたらクリア」といったルールを与えると、AIは失敗と成功を繰り返して、最善の行動パターンを見つけ出すようになります。
4. まとめ:AIって思ったより身近かも?
今回は、AIとは何か、どんなことができるのか、どうやって学習するのかという基本的な部分を紹介しました。
「難しそう」「自分には関係ない」と思っていたAIも、実は私たちの生活のあちこちに存在していて、ちょっとした興味や工夫で活用できる可能性を秘めています。
初心者の私でもできるのか、不安とワクワクを抱きつつ、一歩ずつ進んでいきましょう。
